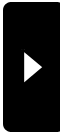2016年10月18日
五老峰~大ガレの頭~毛無山~南西尾根
湯之奥を起点に、前々から登りたかった五老峰、大ガレの頭の二座を経由して毛無山、
そして南西尾根を下って周回してきました。
ヤマレコで見つけた2010年のhansodeさんの記録を参考にしています。
写真は五老峰手前の岩場からの一枚。
富士川の向こうに安倍東山稜が並んでいます。
左手前に見えるのが五宗山です。
※毛無山から南西尾根下降点までの区間以外は、一般登山道ではありません。
道迷いの危険がありますのでご注意ください。

下部温泉、門西家住宅を抜け林道にあるゲート付近に駐車しました。

暫く林道を下り、写真の場所から入山です。

「願かけ地蔵入口」の札があります。

お地蔵さんにお辞儀をして出発です。

標高1000m以上まで、よく整備の行き届いた道が続いています。
写真のバイクとキャタピラは、その整備に使われているようです。

布引山~笊ヶ岳~這松尾、、
左後方に悪沢岳、右手前に富士見山

炭焼き跡

七面山

防獣ネットの張られた伐採地を過ぎると、徐々に踏み跡が消えていきます。

ふり返って、、
二本足では辛い斜度、、九十九折りでも直登でもお好みのコースで、、

冒頭の写真はこの岩場の上からです。


雪見ヶ岳~熊森山~五宗山

キクの仲間が咲いていました。


五老峰、、ごろうぼうと読むようです。

小さな杭が山頂標の代わりでした。ここから毛無山まではテープ類は、ほぼありません。

タマゴタケかな?

大ガレの頭への最後の登りが始まると、ガレ場が増え、景色が広がります。

上河内岳、赤石岳、悪沢岳が顔を出しています。

カケスの羽

大ガレの頭

かすかに読めます。

大ガレの頭からの下降で、少し外してしまい修正しました。
紅葉はちらほら、、今年は本当に今ひとつですね。。

毛無山山頂、、ポカポカ陽気の中、多くの人がランチをとっていました。

富士山は残念!

北アルプス展望台から八ヶ岳連峰、、
南アルプスは雲に呑まれつつありました。

リンドウ

南西尾根への下降(ここも外してしまい、後に修正、、、)を始めたとき、真っ黒な獣が走り始めました、、
熊!!と思いましたがカモシカでした。
この後、更に下ると駆け抜ける5頭以上のカモシカの群れに遭遇、、
ドドドドと走る迫力もなかなかのものでしたが、本来群れることのないカモシカが大量にいることに
驚きました。鹿の群れと違うのは、散り散りに逃げるところでしょうか。


途中から、植林の尾根に代わります。打たれた枝と間伐された木で、なかなか歩きづらいです。。

ということで林道に出ます。あとはゲートまで歩くだけ。

下部温泉会館で汗を流し、、

下部駅前の丸一食堂でほうとうを食べます。
ここのほうとうは本当に美味しくて大好きです。
道迷いの危険がありますのでご注意ください。
下部温泉、門西家住宅を抜け林道にあるゲート付近に駐車しました。
暫く林道を下り、写真の場所から入山です。
「願かけ地蔵入口」の札があります。
お地蔵さんにお辞儀をして出発です。
標高1000m以上まで、よく整備の行き届いた道が続いています。
写真のバイクとキャタピラは、その整備に使われているようです。
布引山~笊ヶ岳~這松尾、、
左後方に悪沢岳、右手前に富士見山
炭焼き跡
七面山
防獣ネットの張られた伐採地を過ぎると、徐々に踏み跡が消えていきます。
ふり返って、、
二本足では辛い斜度、、九十九折りでも直登でもお好みのコースで、、
冒頭の写真はこの岩場の上からです。
雪見ヶ岳~熊森山~五宗山
キクの仲間が咲いていました。
五老峰、、ごろうぼうと読むようです。
小さな杭が山頂標の代わりでした。ここから毛無山まではテープ類は、ほぼありません。
タマゴタケかな?
大ガレの頭への最後の登りが始まると、ガレ場が増え、景色が広がります。
上河内岳、赤石岳、悪沢岳が顔を出しています。
カケスの羽
大ガレの頭
かすかに読めます。
大ガレの頭からの下降で、少し外してしまい修正しました。
紅葉はちらほら、、今年は本当に今ひとつですね。。
毛無山山頂、、ポカポカ陽気の中、多くの人がランチをとっていました。
富士山は残念!
北アルプス展望台から八ヶ岳連峰、、
南アルプスは雲に呑まれつつありました。
リンドウ
南西尾根への下降(ここも外してしまい、後に修正、、、)を始めたとき、真っ黒な獣が走り始めました、、
熊!!と思いましたがカモシカでした。
この後、更に下ると駆け抜ける5頭以上のカモシカの群れに遭遇、、
ドドドドと走る迫力もなかなかのものでしたが、本来群れることのないカモシカが大量にいることに
驚きました。鹿の群れと違うのは、散り散りに逃げるところでしょうか。
途中から、植林の尾根に代わります。打たれた枝と間伐された木で、なかなか歩きづらいです。。
ということで林道に出ます。あとはゲートまで歩くだけ。

下部温泉会館で汗を流し、、

下部駅前の丸一食堂でほうとうを食べます。
ここのほうとうは本当に美味しくて大好きです。
Posted by itta at 21:43│Comments(8)
│天子山地
この記事へのコメント
ここは前々から歩いてみたいと思っていたコースです。
最近、登山口まで車での移動が面倒になりお手軽ハイキングばかりです。
やっぱり歳のせいでしょうかね~。
最近、登山口まで車での移動が面倒になりお手軽ハイキングばかりです。
やっぱり歳のせいでしょうかね~。
Posted by 賢パパ@今日は久しぶりの飲み会 at 2016年10月19日 04:38
ittaさん、こんばんは
山梨を着々と潰していますね。
私のブログ仲間もマイナーな山を楽しみ、最近は新潟遠征が多いです。
百の山に百の喜びあり。 そして四季折々の感動もありますね。
歩かないと解らない。 39度を超える知恵熱でそんなことを・・・
山梨を着々と潰していますね。
私のブログ仲間もマイナーな山を楽しみ、最近は新潟遠征が多いです。
百の山に百の喜びあり。 そして四季折々の感動もありますね。
歩かないと解らない。 39度を超える知恵熱でそんなことを・・・
Posted by 岳 at 2016年10月19日 19:21
>賢パパさん
大ガレの頭は、賢パパさんとのやり取りの中で名前を知ったことを
覚えています。まだ登山を始めた頃です。
車を使わないと、日本平、浜石、竜爪などが多くなりそうですね。
満観峰なども電車でアクセスしやすいですよね!
大ガレの頭は、賢パパさんとのやり取りの中で名前を知ったことを
覚えています。まだ登山を始めた頃です。
車を使わないと、日本平、浜石、竜爪などが多くなりそうですね。
満観峰なども電車でアクセスしやすいですよね!
Posted by itta at 2016年10月19日 20:57
at 2016年10月19日 20:57
 at 2016年10月19日 20:57
at 2016年10月19日 20:57>岳さん
こんばんは。
山梨百名山にもかからない山ですが、登ってみると実に面白いです。
静岡にもそんな山がたくさんあります!
アルプスの迫力、絶景には及びませんが、毎食ステーキよりも
あれこれ手を出すのが性に合っているようです(笑
で、、高熱ですね、、マイコプラズマが流行っているようですので、
お大事にしてください。
こんばんは。
山梨百名山にもかからない山ですが、登ってみると実に面白いです。
静岡にもそんな山がたくさんあります!
アルプスの迫力、絶景には及びませんが、毎食ステーキよりも
あれこれ手を出すのが性に合っているようです(笑
で、、高熱ですね、、マイコプラズマが流行っているようですので、
お大事にしてください。
Posted by itta at 2016年10月19日 21:00
at 2016年10月19日 21:00
 at 2016年10月19日 21:00
at 2016年10月19日 21:00毛無山山頂からは雨ヶ岳の道しか思いつかなかったので、
地理院の地図を見ながら読んでいました。
すると標高1619mの山頂にある三角点の名前が 「五郎坊」 になっています。
ittaさんは 「五老峰、ごろうぼうと読むようです」 と紹介していますが、
五郎坊なら無理なく読む事が出来る。若しや・・・・・・・・
残念ながら五郎坊のヒットはありませんでしたが、
三角点の名称は案外いい加減ですので、あてにはなりません。
検索した中に五老峰の由来は 「岩がゴロゴロした山」 とありましたが、
実際に岩がゴロゴロしていましたか?
地理院の地図を見ながら読んでいました。
すると標高1619mの山頂にある三角点の名前が 「五郎坊」 になっています。
ittaさんは 「五老峰、ごろうぼうと読むようです」 と紹介していますが、
五郎坊なら無理なく読む事が出来る。若しや・・・・・・・・
残念ながら五郎坊のヒットはありませんでしたが、
三角点の名称は案外いい加減ですので、あてにはなりません。
検索した中に五老峰の由来は 「岩がゴロゴロした山」 とありましたが、
実際に岩がゴロゴロしていましたか?
Posted by hagure at 2016年10月20日 09:27
>hagureさん
なるほど、、三角点名は五郎坊ですか。。
hagureさんと同じように、松理さんも三角点名は適当に付けられたり
当て字が多いとよく仰っていますので、実際のところどちらが先か、
私には判断できません。。
岩は1000mを越え、道がなくなると同時に文字通りごろごろと転がって
いました。山頂手前は石というよりも岩でした。
真偽は分かりませんが、こうした考察は面白いです。
日頃から独特の視点で山を楽しんでいらっしゃるhagureさんならではですね!
ありがとうございます!
なるほど、、三角点名は五郎坊ですか。。
hagureさんと同じように、松理さんも三角点名は適当に付けられたり
当て字が多いとよく仰っていますので、実際のところどちらが先か、
私には判断できません。。
岩は1000mを越え、道がなくなると同時に文字通りごろごろと転がって
いました。山頂手前は石というよりも岩でした。
真偽は分かりませんが、こうした考察は面白いです。
日頃から独特の視点で山を楽しんでいらっしゃるhagureさんならではですね!
ありがとうございます!
Posted by itta at 2016年10月20日 20:58
at 2016年10月20日 20:58
 at 2016年10月20日 20:58
at 2016年10月20日 20:58五老峰には登ったことがありますが、その先の大ガレの頭はまだです。
う~ん、いつか行くことがあるかな?
前回はGPSを持つのを忘れたので引き返しましたが
五老峰まででいっぱいいっぱいでした。
充実した山歩きを楽しんでいますね。
う~ん、いつか行くことがあるかな?
前回はGPSを持つのを忘れたので引き返しましたが
五老峰まででいっぱいいっぱいでした。
充実した山歩きを楽しんでいますね。
Posted by ぷぅ at 2016年10月20日 23:26
>ぷぅさん
五老峰までの登りが笑えるくらい急でしたが、
ぷぅさんですと、問題ないですね!
大ガレの頭からの下降で尾根を外しています。
ピークからの下降は、コンパスできちんと確認をとらないと
大抵やらかしてしまう私です。。。
下りの南西尾根は、後半こそ植林で人がたくさん入っていますが、
序盤からしばらくは、ほぼ踏まれていない尾根歩きでした。
真っ直ぐと侮っていましたが、なかなか緊張しました。
五老峰までの登りが笑えるくらい急でしたが、
ぷぅさんですと、問題ないですね!
大ガレの頭からの下降で尾根を外しています。
ピークからの下降は、コンパスできちんと確認をとらないと
大抵やらかしてしまう私です。。。
下りの南西尾根は、後半こそ植林で人がたくさん入っていますが、
序盤からしばらくは、ほぼ踏まれていない尾根歩きでした。
真っ直ぐと侮っていましたが、なかなか緊張しました。
Posted by itta at 2016年10月22日 22:12
at 2016年10月22日 22:12
 at 2016年10月22日 22:12
at 2016年10月22日 22:12